
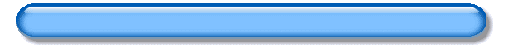

・ 司法制度改革審議会で審議されている「計画審理」とはどのようなものなのでしょうか?
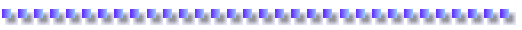
2001年5月14日 弁護士永島賢也
 計画審理については、第54回司改審の配付資料にも触れられていますし、平成12年11月20日の中間報告にも記載されています。
計画審理については、第54回司改審の配付資料にも触れられていますし、平成12年11月20日の中間報告にも記載されています。
中間報告には民事訴訟の充実・迅速化という題目のもとに、「計画審理」と「証拠収集手続の拡充」と、二つの項目のひとつとして掲げられています。
 計画審理については、民事事件を「国
計画審理については、民事事件を「国 民の期待する合理的期間内に終結させるためには、訴訟の早い段階から審理の終期を見通し、手続きの進行過程を計画的に定めた計画審理を実施することが有効」であるとしています。
民の期待する合理的期間内に終結させるためには、訴訟の早い段階から審理の終期を見通し、手続きの進行過程を計画的に定めた計画審理を実施することが有効」であるとしています。
その方策として、
(1)大規模訴訟に関して定められている計画審理の規定を標準的事件にも法律または規則で規定すること、
(2)当事者が準備のため早期に証拠を収集しうる手段を導入すること、
(3)訴訟の類型ごとに標準的期間を定めること、
(4)審理計画を遵守させるための裁判所の訴訟指揮権を強化すること、
などが考えられる提案として掲げられています。
 そのうち、審議会の考え方としては、以下のとおりです。
そのうち、審議会の考え方としては、以下のとおりです。
(1)標準的事件についても、手続の早い段階で裁判所と両当事者との協議に基づき審理の終期を見通した審理計画を定め、それに従って計画審理を実施するとの実務を定着させて行くべきこと。
(2)標準的事件についても法律または規則により審理計画を定めるための協議をすべきこととすること
(3)訴え提起前を含め準備のための早期の証拠収集を可能とするための手段を拡充すること
 (1)・(2)について
(1)・(2)について
おそらく、大規模訴訟に関する民事訴訟規則165条を他の標準的事件にも適用する方向性を打ち出したものと思います。
 規則165条とは、「大規模訴訟においては、裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のために、進行協議期日その他の手続を利用して審理の計画を定めるための協議をするものとする。」と定めるものです。
規則165条とは、「大規模訴訟においては、裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のために、進行協議期日その他の手続を利用して審理の計画を定めるための協議をするものとする。」と定めるものです。
つまり、協議を行って審理計画を立てるというカンファレンス型を念頭においていると考えます。
 (3)について
(3)について
これは、「証拠収集手続の拡充」という項目とも重複するものですが、米国のディスカバリーに相当する制度の可否、その他の証拠収集手段の拡充改善の具体策は、検討課題とされているようです。
思うに、米国のディスカバリー制度導入については、その弊害が指摘されて久しいともいえるので、消極的対応になると考えます。
また、その他の証拠収集手段については、ドイツの独立証拠調べ(ドイツ民事訴訟法485条2項)が参考になると考えます。そのほか、フランスのレフェレ(訴訟提起前鑑定)も参考になると思います。
 ドイツの独立証拠調べは、鑑定人による書面による鑑定を求めることができ、その要件となる法律上の利益は、請求原因となるべき事実の一部が鑑定事項になっていれば足りると解されているとのことで、訴訟の回避に役立ちうる場合には法律上の利益があるものとみなされています。その意味で、我が国の証拠保全の要件よりずっと緩やかといえます。
ドイツの独立証拠調べは、鑑定人による書面による鑑定を求めることができ、その要件となる法律上の利益は、請求原因となるべき事実の一部が鑑定事項になっていれば足りると解されているとのことで、訴訟の回避に役立ちうる場合には法律上の利益があるものとみなされています。その意味で、我が国の証拠保全の要件よりずっと緩やかといえます。
 フランスの鑑定レフェレ(同法145条)は、「本案訴訟提起前に、紛争解決に必要となりうる事実の証拠を保全し、または証明を行う(conserver
ou etablir lapreuve de faits)正当な理由が存在する」ことを要件としています。
フランスの鑑定レフェレ(同法145条)は、「本案訴訟提起前に、紛争解決に必要となりうる事実の証拠を保全し、または証明を行う(conserver
ou etablir lapreuve de faits)正当な理由が存在する」ことを要件としています。
これも我が国の証拠保全の要件よりも緩やかな定めといえ、運用も「紛争が存在」し「本案訴訟での審理に必要となりうる」のであれば「正当な理由」があるとされているとのことです。
これは、証拠保全機能を超え、専門的知見を有する公正中立な第三者である鑑定人の見解が早期に示されるため、本案訴訟前に合意による解決が可能になっているようです(なお、ENEとENEE)。
ただ、いずれの制度も、医療過誤訴訟については、その運用が活発であるとはいえないようです。
いよいよ、近日中には、司改審の最終報告が明らかになる予定です。
参考文献「司法制度改革審議会平成12年11月20日中間報告」・「専門的な知見を必要とする民事訴訟の運営(法曹界)」山本和彦「民事訴訟審理構造論」
 ENEE=(Early Neutral Expert Evaluation)古閑祐二・「アメリカ合衆国における民事司法改革・アメリカにおける民事訴訟の実状」「21世紀の民事訴訟の構想・日弁連法務研究財団)」アメリカ合衆国における専門アドバイザー(Technical
Advisor)及び早期中立的評価(Early Neutral Evaluation)を参考にしたものであるとのことです。
ENEE=(Early Neutral Expert Evaluation)古閑祐二・「アメリカ合衆国における民事司法改革・アメリカにおける民事訴訟の実状」「21世紀の民事訴訟の構想・日弁連法務研究財団)」アメリカ合衆国における専門アドバイザー(Technical
Advisor)及び早期中立的評価(Early Neutral Evaluation)を参考にしたものであるとのことです。
 「審理の終期を見通した審理計画」
「審理の終期を見通した審理計画」
この点については、異論があり得ます。訴訟手続の早期に証拠調べの具体的な日程や更に最終弁論期日まで決定するという趣旨であれば、そのような審理計画をたてても、結局事後的な変更を許してしまうおそれがあります。というのは、フランスでは、呼上期日の段階で一気に最終弁論期日までが手続契約によって決定されるとのことですが、そこでは、通常の民事訴訟の多くで書証が決定的な役割を果たし、証人尋問の証拠調べにしめる役割が小さく、損害賠償事件などでも鑑定が証拠の中枢をなすなど、我が国と比較してはるかに証拠調べ期間の予測可能性が高いという事情があります。
フランスでは、原則として書証の内容に反した立証主題またはその内容以外の立証主題のための人証は許されず(民法1341条1項)、例外は、5000フラン未満の場合(同条同項)、書面による立証の端緒の存する場合(1347条)、債権者の書証取得が不可能な場合(1348条)、商事事件に関する場合(商法109条)などに限られているとのことです。
そうだとすると、我が国においては、答弁書が提出された後の審理計画を立てる期日には、弁論進行段階(争点決定の直前)までの審理計画について合意しておくのが、実状に即していると思われます。
以上は、山本和彦(東北大学法学部助教授・当時)・「民事訴訟審理構造論・日本法ー審理契約論の提唱」405頁によっています。
なお、山本教授は、審理契約に関し新たに論文を公にしています。
「審理契約再論・合意に基づく訴訟運営の可能性を求めて」
法曹時報 第53巻5号

関連論文
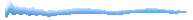
山本和彦(一橋大学大学院教授)
「審理契約再論・合意に基づく訴訟運営の可能性を求めて」
法曹時報・第53巻5号
(平成13年5月1日発行)


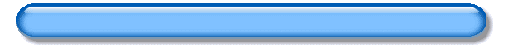
 民の期待する合理的期間内に終結させるためには、訴訟の早い段階から審理の終期を見通し、手続きの進行過程を計画的に定めた計画審理を実施することが有効」であるとしています。
民の期待する合理的期間内に終結させるためには、訴訟の早い段階から審理の終期を見通し、手続きの進行過程を計画的に定めた計画審理を実施することが有効」であるとしています。 規則165条とは、「大規模訴訟においては、裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のために、進行協議期日その他の手続を利用して審理の計画を定めるための協議をするものとする。」と定めるものです。
規則165条とは、「大規模訴訟においては、裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のために、進行協議期日その他の手続を利用して審理の計画を定めるための協議をするものとする。」と定めるものです。