

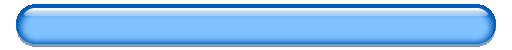
| 51 | 3.13 | 訴訟手続への新たな参加制度・ 福岡地方検察庁前次席検事による捜査情報漏えい問題について |
| 52 | 3.19 | 福岡高等裁判所判事に関する捜査情報漏洩証拠隠滅問題 司法制度とADRのあり方 労働関係事件への対応強化 |
| 53 | 3.27 | 警察庁からのヒヤリング 刑事裁判の充実迅速化 |
| 54 | 4.6 | 弁護士費用の敗訴者負担(訴訟費用化) 裁判所の配置利用窓口 懲罰的損害賠償制度 クラスアクション制度(団体訴権制度) 民事訴訟の充実・迅速化 専門的知見を要する事件への対応強化 (専門委員参加制度など) 知的財産権関係事件 (東京大阪両地裁への専属管轄化など) 労働関係事件 |
| 55 | 4.10 |
検察審査会 |
| 56 | 4.16 | 弁護士任官推進のための最高裁・日弁連の協議 裁判官の人事制度の見直し |
| 57 | 4.24 | 「裁判所・検察庁の人的体制の充実」について 「法曹養成に関する審議の取りまとめ」について 「法曹人口に関する審議の取りまとめ」について 「最終意見項目案」について 「 最終意見の項目」について |
| 58 | 5.8 | 「弁護士任官の推進及び裁判官制度改革」について「司法の行政に対するチェック機能の在り方」について 「最終意見項目案」について 「最終意見後の改革推進体制及び改革実現後の継続的改革・改善の推進体制の在り方」について |
| 59 | 5.21 | (第1読会) |
| 60 | 5.22 | (第1読会) |
| 61 | 5.29 | (第2読会) |
| 62 | 6.1 | (第3読会) |