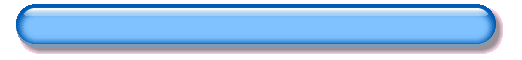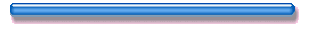 弁護士永島賢也 2003年8月12日
弁護士永島賢也 2003年8月12日


最高裁判所の昭和51年3月10日判決(大法廷・民集30-2-79)は、特許審決取消訴訟の審理範囲の制限に関する有名な判例です。

「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない」とするものです。

簡単にまとめると、その審判手続にいて現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされ、それ以外の無効原因については、訴訟においてこれを審決の違法事由として主張したり、裁判所の判断を求めたりすることはできないという意味です。

これは、訴訟の前段階において専門行政庁(特許庁)による慎重な審理判断を受ける利益を害しないため、審理の対象を限定しましょうというものです。

確かに、審判手続で現実に争われず、審理判断もなされていない事由について、その審決取消訴訟の場で裁判所に、いきなり認定・判断されてしまうことがあっては、その事由について、事前に行政庁での専門判断を受けられなかったことになってしまいます。

ところで、同じく最高裁平成4年4月28日判決(民集46-4-245)の補足意見(園部氏)は、「最高裁判所昭和五一年三月一〇日大法廷判決(民集三〇巻二号七九頁)の判旨から見ても、再度の審判において、当事者双方による新たな主張立証が行われ、事案によっては更に手続が反復されることにより、無効審判及び審決取消訴訟が際限なく続けられる可能性を否定することができない。」と述べられています。

これは、審判対象を限定的にすると場合によって、かえって、実質的には同一の紛争といえるものが、特許庁と裁判所との間をキャッチボールのように行ったり来たり際限なく反復してしまうという可能性(総合的な紛争の解決は長引くことになります)を指摘したものといえます。

現在、民事訴訟の充実化、迅速化を図ることを目的として法律の改正が行われていますが(特に知的財産権訴訟については東京高等裁判所の専属管轄化などが画期的です)、上記のような同一紛争のキャッチボールの問題は視野に入っていないようです。

いわゆるキルビー特許事件(最高裁平成12年4月11日判決・民集54-4-1368)では、「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができ」、権利濫用にあたる場合は、特許の有効性について実質的に一挙的解決(権利濫用を理由とする請求棄却)を実現することができるとされていることと対照的でもあります(侵害訴訟vs審決取消訴訟)。

専門行政庁による事前の専門判断を受ける利益を強調するのであれば、上記のようなキャッチボールも致し方のないことなのかもしれません。

ところで、上記最高裁平成4年4月28日判決は、
「特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法33条1項の規定により、右取消判決の拘束力が及ぶ。
そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。
したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは右主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができないのは当然である。」

と述べています。

この行政事件訴訟法33条1項は、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めています。

簡単に言えば、裁判所で審決が取り消された場合、行政庁はこの判断に拘束されますよ、判決と違うことを言ってはだめですよ、ということです。

そして、その拘束する力が及ぶのは、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定と法律判断にわたるとされています。

このように行政庁(審判官)が裁判所の判決に拘束されてなされる再度の審判や、再度の審決取消訴訟においては、もはや、当事者がこれを再び争って立証活動を行うことは許されないことになります。

ところで、上記最高裁昭和51年判決は、上記のとおり審理の対象を限定的にとらえます。

他方、上記最高裁平成4年判決は、拘束力の範囲を結論を導くうえで必要な事実認定と法律判断にわたるとしています。

この点に何か問題はないでしょうか?審理対象は小さく狭く、切り取られていますが、行政事件訴訟法33条1項の拘束力の範囲は、それよりもずっと大きく広いということになりそうです。

例えば、ある審理対象が「(A)ではない」という主文を導くために、その審理対象が、他の独立して審理対象になりうる事由「(B)である」からという理由が述べられていた場合はどうでしょうか?

最高裁昭和51年判決によれば、審理対象は(A)についてのみです。他方、行政事件訴訟法33条1項により、(B)であるからという事実認定・法律判断にも拘束力が及ぶことになります。

すなわち、行政庁は、「(A)でない」という点と、「(B)である」という点の両方について拘束されそうです。

しかも、行政庁が、判決に拘束されて「(B)である」という審判を出す場合、当事者は、もう、「(B)でない」という主張立証を許してもらえないことになるでしょう。その後の再度の審決取消訴訟でも同様です。

もし、そうだとすると、当事者は、(B)であるかどうかという判断については、結果として、訴訟になる前に専門行政庁による事前の専門判断を受けられなかったことになります。

このような結果は、上記最高裁昭和51年3月10日判決の趣旨に反するでしょう。

こうしてみると、審決を取消す旨の判決がなされた場合、たとえ、その理由中の判断に独立して審理対象になりうる事情(他の無効原因など)にふれた事実認定や法律判断があっても、行政庁は、これを無視し、現になされた審理対象についてのみ判断すべきということになります
(なお、「審判は審決によって終了する(同法157条1項)」ところ、裁判所で特許庁の処分を取り消す旨の判決がなされて確定しても、それだけでは、まだ、審判は終了してはいないことになりますので、引き続き審判官による審理が行われなければならないことになります。特許法181条2項参照)

このような自体は果たして現実問題として生じうるのでしょうか?

商標権に関しては可能性があるといえます。たとえば、記述的商標に該当するという無効審決を取消す判決の理由中に当該商標は普通名称に該当するので記述的商標とはいえないと判断されていた場合などです。
以 上
(次)
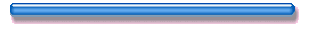
Copyright © 2003 kenya Nagashima , all rights reserved.